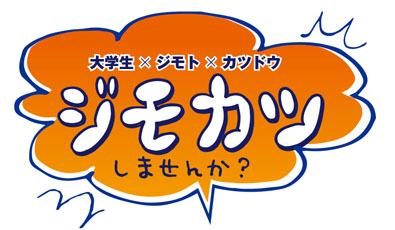DIG~地域の人と学ぶこと~
2013年10月9日に稲田中学校で行われた特別授業に参加してきました!
そもそもDIGとは【Disaster(災害) Imagination(想像力) Game(ゲーム)】と書き、災害想像ゲームとも言われています。主に真っ白な地図を用いて地域で大きな災害が発生する事態を想定し、地図に直接、または透明のシートを被せそこに災害時に予測される被害や避難所への避難ルートなどを書き込み、気付いたこと、問題点に対する改善案などを紙に書いていく訓練です。DIGはハザードマップの役割もはたします。
この特別授業は、多摩消防署と中学校、地域が連携し、区内の中学校で初めて開催されるものです。
この日は生徒7~8人、町会の方が2~3人、消防署員2人でグループとなり、訓練を行いました。
~DIG説明 地図作成~

消防隊員からDIGの説明を聞く生徒たち

町会の人も一緒に参加

町会の方のアドバイスを聞く生徒

生徒たちを見つめる三竹会長

消防隊員の話を真剣に聞く生徒たち

種類ごとに色分けされた地図
~発見を共有~

最後はグループごとに発表しました!
~地域の人と一緒に考える~
今回の特別授業において最も大事だったこと、それは生徒たちが消防署員や地域の方々と災害時にどのようなことが起こるのか一緒に考えることです。消防署員からは災害が起こった際にどのような被害が想定されるかなど、ポイントを教えてもらいました。また、普段から宿河原地区を美化活動や防犯防災活動などで細かく知り尽くしている町内会の方のアドバイスがあることにより、より発展的な訓練になり、かつ、地域の人と関わることにより、災害時の避難や避難先での生活を円滑に進めることが可能になります。このような機会を設けることはとても大変ですが、とても大切なことだと思います!